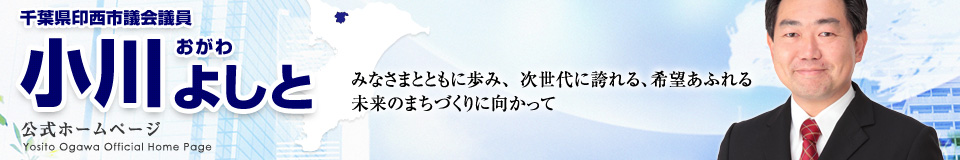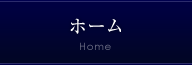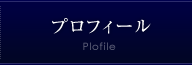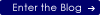- 小川よしと公式ホームページ>
- 議会活動>
- 平成22年定例会議一般質問
平成22年定例会議一般質問
平成22年第4回定例会
- 1.環境問題について
- (1)印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例について
- (2)クリーン印西推進運動について
- (3)ごみの更なる分別について
- (4)再資源化率について
- (5)廃食油の回収事業について
- (6)不法投棄について
- 2.地域活性化に向けた取り組みについて
- (1)地域ブランド創出について
・農産物について
・商工について
・その他
- (2)原動機付自転車のナンバープレートについて
- 3.窓口サービスについて
- (1)やさしくて便利な窓口づくりについて
市民部長 平成22年4月より総合案内業務を市民課窓口業務の一環として、職員による業務とし、担当している。 来庁者が最初に訪れるところであり、重要な業務なので、問合せに対応できるように心がけている。来庁者に満足いただけるサービスを提供していきたい。 出生時に住民登録のための住民異動の届出用紙は、現在4枚複写となっており、各部門に回付され、別に申請書を記入することなく、利便が向上している。 総務部長 障がいをお持ちで車イスでの来庁者に支障がないよう、出入り口のスロープ設置や、申請窓口を1階に集約し、車イスの高さのローカウンターを設置した。 また、提案のあった各部署までの色別誘導線や部署ごとの色別標示については、現在、吊下げ標示板を採用しており、そのなかで、利用者にわかりやすいサインを設置していきたい。
- 4.安心・安全な街づくり
- (1)元一休地先、市道114・116・210号線交差点改良事業と信号機の設置について伺う。
- (2)市道116号線の道路整備、歩道整備について伺う。
平成22年第3回定例会
- 1.新市熟成の取り組みについて
- (1)公共施設の利用について
- (2)ふれあいバスについて
- (3)市民活動について
・町内会自治会活動について
・各地域の行事について
- 2.道路整備について/dt>
- (1)国道464号・北千葉道路について
- (2)(仮称)コスモス通りについて
- (3)南環状線・北環状線について
- (4)市道00-031号線について
- (5)市道物木滝線について
- (6)その他の主要道路について
- 3.教育課題について
- (1)中1ギャップについて
教育長 小学校から中学校への生活環境の変化に適応できず、不登校となる「中1ギャップ」の解消を図るため、小・中学校のきめ細やかな連携と対応が重要になる。 各学校において、入学前に小・中連絡会議を実施し、小学校での学習や生活状況等の情報交換を行い、中学校での適切な受け入れができるように努めている。 また、児童生徒や保護者が気軽に悩みなどを相談できる体制づくりに努めている。今後も、小・中学校の円滑な連携を図り、「中1ギャップ」の対応に努めたい。 - (2)小中一貫教育について
印西市においては、現行の教育制度を引き続き展開している。同一の小学校の卒業生がそのまま一つの中学校に進学するようになっていて、施設は別々であるが、小中一貫校に近い形態になっている。 以前より、子どもたちが小学校から中学校への円滑な接続が図られるように、小・中連携事業を実施し、小中一貫教育に劣らない体制づくりの構築に努めている。 学習面では、交流事業や指導方法等の共通理解を図り、生活面では合同事業や交流事業等を展開している。今後も、子どもの豊かな成長に視点を置いた教育活動を通じて、9ヵ年の義務教育の充実に努めていく。
平成22年第2回定例会
- 1.人権問題について
- (1)人権侵害被害への対応について
- (2)人権教育・啓発への対応について
- (3)個別重要課題ごとの施策について
・女性
・子ども
・高齢者、障害者
・特定疾病感染者
・その他、新しい人権課題など
- 2.固定資産税の課税過剰請求について
- 本年3月、平成21年度の市街化調整区域の固定資産税に課税ミスがあり、過剰に請求したと発表した。そこで、>
- (1)原因追及について
市民部長 ①市民のみなさまの信頼を損ね、また、対象となる方々に多大なる迷惑をかけ、申し訳なかった。 本年2月、固定資産税オンラインシステムの委託会社より、平成21年度の固定資産税の土地の評価計算にプログラムミスがあったと報告を受けた。 内容については、土地の評価額を算定する際、補正適用率に誤りがあった。 その結果、高い評価額及び税額となった。課税誤りの対象者は418名、過剰に請求してしまった税額は約174万円である。 誤りの原因は、プログラムミスに対し職員のチェックの徹底不足によるものである。 - (2)今後の対策について
再発防止策としては、チェックの重要性を深く認識し、プログラムの仕様の打合せを入念に行う。 変更箇所に対して、市と委託会社とで共通認識を持つこととし、複数職員によるチェック体制を徹底する。 また、計算プログラムの変更に併せてモデルケースを作成、試算するなどして、検証の精度をより一層高めることとする。二度と無いよう、再発防止に万全を期していく。
- 3.庁内情報通信ネットワーク(庁内LAN)について
- (1)新市移行時について
(2)庁内LANの安定運用までのスケジュールについて
(3)庁舎改修に伴う電算室移設について
平成22年第1回定例会
- 1.地域ブランド創出事業について
- 平成20年7月に執行された印西市長選挙の際、山﨑市長がマニフェスト(政権公約)に掲げられたなかの大項目の一つとして、『「いんざい」を多彩な産業が育つ活力あるまちへ』とあります。 そのうちの小項目の一つとして、「地域ブランドの創設及びブランド化に向けた商品開発を支援します。」とあります。 平成20年第3回定例会の個人質問でも伺っておりますが、その後の取り組みについて伺います。
- (1)農産物等のブランド化基本方針について>
- (2)印西市における「いんざいブランド」の育成支援について
- (3)印西市と商工会による支援について
- (4)特定商品の特区の推進について
- (5)農商工等連携促進事業について
- (6)特産品認定について
- 2.防犯活動について
- 先に述べたマニフェスト(政権公約)に掲げられたなかの大項目の一つとして、 『「いんざい」でやすらぎと安心・健康を手に入れよう』とあります。そのうちの小項目の一つとして、「自主防犯活動への支援を継続して行います。」とあります。 印西市の取り組みについて以下のとおり伺います。
- (1)印西市の自主防犯活動への支援について
- (2)自主防犯活動の状況把握について
- (3)防犯活動による成果について
- 3.子どもたちの安全対策について
- 平成20年第2回定例会の個人質問でも伺っておりますが、その後の取り組みについて伺います。
- (1)通学路の安全点検および危険箇所の改善について
教育部長 登下校の指導をしたり、保護者の協力による校外パトロールをして、危険箇所の確認をしている。 PTAの協力による通学路の除草や通学路の拡幅等の改善が図られている。小学校では、子どもの視点で通学路を点検し、地域情報を収集し、学校ごとの安全マップを作成している。 4月には、新しい安全マップを配布予定である。印旛・本埜地区は2学期中を目途に、作成を予定している。 - (2)防犯ブザーの運用状況について
児童生徒の登下校時の安全確保のために、小学校入学時に全児童に防犯ブザーを渡している。 各学校で、防犯教室で使い方を指導し、各家庭に定期的な点検を呼びかけ、非常時に備えている。 現在、本埜地区は無償貸与しているが、印旛地区では行っていないので、平成22年度より貸与を予定している。 - (3)学校安全防犯メールシステムの運用状況について
平成19年度に導入し、保護者に防犯情報や安全情報を中心に活用している。20年5月末の登録率は59%であったが、保護者への呼びかけにより、今年2月の調査では78%と登録率が大幅に向上した。1校あたりの年平均7.6回だった利用回数も。20.8回に伸びた。 不審者、風水害への対応、部活動の連絡等に活用しているが、21年度は、インフルエンザの情報提供で活用する機会が多くなった。印旛・本埜地区においては、今後、早い段階で整備できるよう準備をしている。 - (4)登下校通知システムの導入について
ICチップ内蔵のカードをかざすことにより、保護者に子どもの登下校情報をメール配信できる通知システムについても、今後研究したい。